本編に入る前に
執筆時期
この記事は2025年6月18日時点で執筆されたものになる。変更されている場合もあるため、その点についてはご了承いただきたい。
本記事は
子供たちの安全やシビアにならなければならない個人情報の取り扱いなど、IoTがどのように管理・運用されているかを紹介する。安全上の観点から画像などの具体的な内容をお伝えすることができない場合があるため、その点についてもご了承いただきたい。
本記事について
昨今、少子高齢化により労働人口はどの界隈でも不足してきている。それはキッズクラブでも同じである。精神的にも身体的にも未熟な子どもたちの安心と安全を守るため、どのようなIoTが使われているか。キッズクラブの現状を少しでも理解していただけたらと思い、この記事を書くに至った。
放課後キッズクラブの概要
放課後キッズクラブについて
私は現在、横浜市の放課後キッズクラブにアルバイトという形で従事している。
簡単に横浜市の放課後キッズクラブについて紹介していこうと思う。
放課後キッズクラブは、小学校施設の一部を借りて実施されている。
①全ての子どもたちを対象に無償で「遊びの場」を提供すること、②留守家庭児童を対象に「生活の場」を提供することを目的としている。
その中で放課後キッズクラブの参加形態には区分というのがあり、
- 「わくわく【区分1】」
- 「すくすく(ゆうやけ)【区分2A】」
- 「すくすく(ほしぞら)【区分2B】」
の3つに分けられる。区分毎に預かることのできる時間や提供されるサービスに違いがある。
「わくわく【区分1】」
平日は放課後から午後4時まで。土曜日の参加は不可。
しかし、キッズクラブで行われるイベントに基本的に参加することができる。
わくわく【区分1】は「遊びの場」として実施している。このため、災害時・熱中症警戒アラート発令時・感染症対策等により実施しないことがある。
「すくすく(ゆうやけ)【区分2A】」
平日は放課後から午後5時まで。土曜日は午前8時30から午後5時まで。
土曜日を除いた学校休業日(運動会などの振替休日や夏休み・冬休みのような長期休み)は午前8時から午後5時まで利用可。しかし、季節によって日没時間が変わるため最終時間が変動する。
延長料金が発生するが、最大午後7時まで延長することが可能。
「すくすく(ほしぞら)【区分2B】」
平日は放課後から午後7時まで。土曜日は午前8時30から午後7時まで。
土曜日を除いた学校休業日は午前8時から午後7時まで利用可。
わくわくは「遊びの場」とされているが、すくすく(ゆうやけ)(ほしぞら)は「遊びの場」及び留守家庭児童のための「生活の場」として実施されている。そのためわくわくと比べて長く預けることが可能になる。また、すくすく(ゆうやけ)(ほしぞら)にはおやつを提供している。アレルギーにより食べられない児童が出てくることはあるが(その場合アレルギー物質が含まれないおやつを提供する)、児童に第2の「生活の場」を提供するという取り組みの一環となっている。
※わくわくも保護者の一時的な用事により留守家庭児童として預けたいという時のために、別途利用料は発生するがすくすく(ほしぞら)と同じ時間まで預けることができる。おやつも提供される。(スポット利用)
これらが横浜市の放課後キッズクラブの簡単な概要となっている。
実際に使用されているIoTの紹介
放課後キッズクラブという場である以上、多くの児童がこの放課後キッズクラブを利用している。となると当然重要になるのが、児童を預かっている際の管理方法である。2022年度に行われた文部科学省の学校基本調査で、全国の小学校の1学級が約22人とされた。これを1学年に3学級、それを6学年とすると全校生徒の数は約396人となる。私が従事しているキッズクラブの平日では約120人の利用者がいる。これはおよそ全校生徒の約3分の1に当たる。この多くの児童を管理するために使われているのが、横浜市のキッズクラブで導入されている、「放課後e-場所システム」である。
児童にマンツーマンで職員が付くことができるわけもなく、一々児童から帰宅について聞くことは非効率極まるし、1・2年生のような低学年となると「わからない」と答える児童がほとんどになる。この「放課後e-場所システム」は主に入退室管理に使用されており、児童が持参する参加カードに貼付されているバーコードを読み取ることでその日に参加している児童を把握、児童の帰り方も児童のみで帰宅する場合と保護者がお迎えにくる場合があるため、帰宅時間と帰り方も確認することができる。この帰宅情報は事前に保護者がサイトから登録する必要がある。児童の帰宅情報が分からなければ帰すことは安全上よろしくないので、登録が済んでいなければキッズクラブ側が保護者へ確認を取らなければならない。また、児童がキッズクラブ中に怪我やトラブルが起こった際にも保護者への迅速な連絡が必要になる。この児童の緊急連絡先や児童の個人情報もまた「放課後e-場所システム」で管理をしている。
他にはどの区分なのか、スポット参加をしているしていない、延長をしているしていない、おやつを食べた食べていない。この違いで利用料が変わるため、保護者側はこのサイトで月々の利用料を確認することができる。
まとめ
今回は簡単にだが放課後キッズクラブの概要、放課後キッズクラブで使用されている「放課後e-場所システム」を紹介した。
筆者が放課後キッズクラブを利用していた頃とは、明らかに利用している児童の数は増加している。これは共働き世帯が増え、留守家庭児童の増加が原因と考えられる。しかし、現代日本は少子高齢化社会であり、労働人口の減少がキッズクラブでも顕著に問題化している。このような事業所は今となっては珍しくないが、現状の放課後キッズクラブについて読者の方々に一考していただけたらと思う。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
引用・参考文献
- 「横浜市-放課後キッズクラブ」(https://www.city.yokohama.lg.jp/)

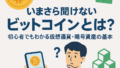

コメント